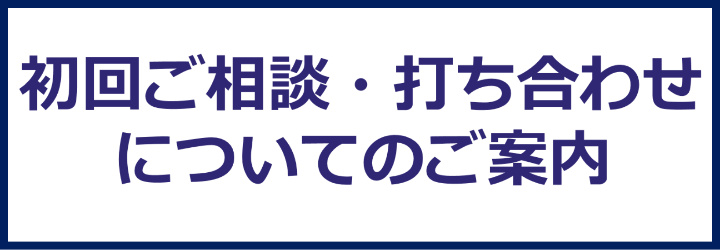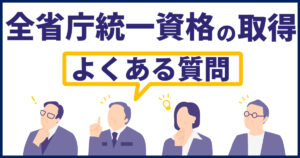
(文章で読むのは苦手・動画でサクッと理解したいという人へ)
全省庁統一資格の仕組み・取得方法・よくある質問について、専門家である行政書士法人スマートサイドが動画で簡単に解説しました。まずは、動画をご覧いただき、さらに詳しい疑問点については、ページ下部の『【Q&A:よくある質問】』をご覧ください。
(解説動画:全省庁統一資格の取得方法とよくある質問)
行政書士法人スマートサイドは、全省庁統一資格の取得手続きの専門家として、ご依頼から最短1週間で申請を完了させる【特急プラン】をご用意しております。「急いで全省庁統一資格を取得したい」「手続きは専門家に外注したい」という人は、こちらのページから、全省庁統一資格の取得手続きをご依頼ください。

省や庁の入札に参加するための「全省庁統一資格の取得手続き」の専門家。必要書類の取得や申請手続きの代行については、もちろんのこと、等級格付の知識もあり、電子入札のための環境設定も一貫してサポート可能。複数名の専門スタッフによるチーム体制で受任するため、急ぎの案件にも対応できるのが事務所の強み。「全省庁統一資格の取得ガイド」を出版。
1.解説動画の内容まとめ(ポイント解説)
ポイント①:この資格ひとつで、全省庁の入札に参加できる
国の機関である「省」や「庁」の入札に参加するための資格を全省庁統一資格と言います。全省庁統一資格を取得すると「国土交通省」「環境省」「防衛省」「自衛隊」「海上保安庁」「デジタル庁」など、さまざまな国の機関の入札に参加することができるようになります。
| 全省庁統一資格を取得する入札に参加できる国の機関 | |||
|---|---|---|---|
| 衆議院 | 参議院 | 国立国会図書館 | 最高裁判所 |
| 会計検査院 | 内閣官房 | 内閣法制局 | 人事院 |
| 内閣府本府 | 宮内庁 | 公正取引委員会 | 警察庁 |
| 個人情報保護委員会 | カジノ管理委員会 | 金融庁 | デジタル庁 |
| 復興庁 | 総務省 | 法務省 | 外務省 |
| 財務省 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 |
| 経済産業省 | 国土交通省 | その他、外局および付属機関など | |
この他にも、独立行政法人、国の研究機関、国立大学などが、入札に参加するための条件として、全省庁統一資格の取得を求めることがあります。
ポイント②:参加できる4つの種類
全省庁統一資格を持つと、「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供」「物品の買受」といった4つの種類の入札に参加できるようになります。
| 入札に参加できる種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 物品の製造 | 衣服、その他繊維製品類/紙、加工品類/車両類など |
| 物品の販売 | 一般、産業用機器類/医療用機器類/事務用機器類など |
| 役務の提供 | 広告、宣伝/情報処理/建物管理等各種保守管理など |
| 物品の買受 | 立木竹、その他 |
全部で60個以上の品目に分かれています。手引きやマニュアルで詳細を確認すると、きっと、御社の得意とする分野が見つかるのではないでしょうか?
ポイント③:申請方法は「郵送」か「ネット」
全省庁統一資格を取得するための申請方法は、「郵送申請」と「インターネット申請」の2つがあります。
| 申請方法 | メリット・デメリット |
|---|---|
| 郵送申請 |
(メリット) 申請書類のひな型をホームページからダウンロードして、手書きで申請書類を作成することができるので、間違いに気づきやすく、パソコンが苦手な人でも、申請をすることができます。 (デメリット) 受付窓口に郵送するため、レターパックなどを購入し、ポストに投函するという手間がかかります。 |
| インターネット申請 |
(メリット) 書類のプリントアウトや郵送という手間がないので、手軽に申請作業を行うことができます。 (デメリット) パソコンが苦手な人は、必要項目の入力が難しく感じます。また、手引きを見ながら、パソコンの画面に向かって入力するため、長時間になると意外と疲れるというデメリットがあります。 |
なお、初めて申請する人は、申請書類をダウンロードして手引きを見ながらゆっくり進めることができるという点において、郵送申請の方が、簡単に感じるかもしれません。
2.【Q&A】全省庁統一資格の取得方法に関するよくある質問
弊所に全省庁統一資格の取得手続きをご依頼になる人から、よくいただく質問をまとめました。「全省庁統一資格の取得方法」をインターネットで検索されている方が、特につまずきやすいポイントです。
Q1:全省庁統一資格を取得するための必要書類は?
全省庁統一資格を取得するための必要書類は「登記事項証明書」「納税証明書その3の3」「納税証明書その2」「財務諸表」の4点です。税金の未納があると「納税証明書その3の3」を取得することができません。
| 必要な書類 | 取得方法など |
|---|---|
| 登記事項証明書 |
法務局で取得できます。申請書に記載した内容と、登記事項証明書に記載されている御社の情報に齟齬がないか?確認をするために必要になります。 また、取締役をはじめとした役員の情報も確認の対象になります。 |
| 納税証明書その3の3 納税証明書その2 |
税務署で取得できます。法人税や消費税に未納がないことを確認するために必要になります。税金に未納があると「納税証明書」を取得することができないため、必ず、税金に未納がないことを確認する必要があります。 |
| 財務諸表 |
会社の「流動資産」「流動負債」「純資産」「売上高」などを確認するために必要になります。上記の「流動資産」などの情報は、「A」「B」「C」といったランクの格付けに影響する数字です。 決算の内容が悪いとランクが低くなりますので、格付けの基準についても、把握しておくとよいかもしれません。 |
Q2:税金に未納があると取得できませんか?
全省庁統一資格を取得するには「納税証明書その3の3」(=税金に未納がないことの証明書)と「納税証明書その2」が、必要です。税金に未納があると、「税金に未納がないことの証明書=納税証明書その3の3」を取得することができず、全省庁統一資格を取得することができません。事前に必ず、税金に未納がないことを確認しましょう。
Q3:会社を作ったばかり(新設法人)でも取得できますか?
A:はい、可能です。設立直後で決算を迎えていない法人でも、全省庁統一資格は取得可能です。ただし、提出書類や入力内容が既存法人とは異なりますので、ご不安な場合は弊所へご相談ください。
Q4:日本国内に登記のない外国法人でも取得できますか?
A:はい、可能です。日本国内に登記のない外国法人でも全省庁統一資格の取得は可能です。ただし、登記簿謄本や納税証明書については、本国発行のもののみならず、日本語に翻訳したものの提出が必要になります。
Q5:資格を取得すれば、すぐに電子入札ができますか?
A:いいえ、別途設定が必要です。全省庁統一資格の取得(=入札参加資格者名簿への登録)と、電子入札システムへの接続は別の手続きです。実際に電子入札を行うには、資格取得後に「ICカード(電子証明書)の購入」や「パソコンの環境設定」「利用者登録」を行う必要があります。
| 電子入札に対応するための手続き | |
|---|---|
| 1.電子証明書の取得 | 電子入札に対応するためには、電子証明書とICカードリーダを購入しなければなりません。電子申請は、パソコンを通じて行うため、事前に電子証明書とICカードリーダの準備が必要になります。 |
| 2.PC環境の設定 |
購入した電子証明書とICカードリーダを御社のパソコンで利用できるようにするための、パソコンの環境設定を行います。電子証明書とICカードリーダをパソコンに接続し、ログインできるような状態にしなければなりません。 このPC環境の設定が、うまく行かないと「ログイン画面が出てこない」「ログインしても画面が進まない」といった操作エラーが発生します。 |
| 3.利用者登録 |
上記のパソコンの設定が終わったら、「調達ポータル」というサイトから、電子証明書の利用者登録をする必要があります。利用者登録が完了しないと、入札の電子申請を行うことができません。 |
| 4.動作確認 |
動作確認を行い、うまく作動すれば完了です。 |
Q6:自分でやるのと専門家に頼むのと、何が違いますか?
A:「時間」と「確実性」が違います。ご自身で行う場合、マニュアルの読み込みや書類収集に数日〜数週間の時間がかかります。専門家に依頼すれば、財務諸表を送るだけで、最短1週間で申請が完了します。「本業に集中したい」「ミスなく確実に取得したい」という方は、専門家への依頼がコストパフォーマンスの面でも優れています。
3.行政書士法人スマートサイドへのご依頼・費用
動画やQ&Aを見ても「やっぱり手続きが難しそうだ」「自分でやる時間がない」と感じた方は、行政書士法人スマートサイドにお任せください。動画で解説している通り、面倒な手続きはすべて代行いたします。
(料金表)
| 項目 | 詳細 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 全省庁統一資格の取得 | 行政書士報酬として | 110,000円 |
| 納税証明書(その3の3)1通 | 法定必要書類として | 2,200円 |
| 納税証明書(その2)1通 | 法定必要書類として | 2,200円 |
| 履歴事項全部証明書1通 | 法定必要書類として | 2,200円 |
| 費用の合計 | 116,600円 | |
(特急プラン)
「1週間以内に申請を完了させたい」というお急ぎのお客さま向けに、最優先で手続きを行う特急プランもご用意しております。
| 1週間以内に申請を完了させたいという急ぎのお客さま向け | |
|---|---|
| 特急プラン | 上記費用+55,000円 |
(ご依頼の方法)
弊所では、申請までのスピードと申請手続きの正確性を両立させるため、電話でのお問合せ・ご相談・ご質問は、承っておりません。複数の専門スタッフによる情報共有を徹底し、時間のロスをなくし少しでも早く申請を行うため、文章(メール)でのやり取りを徹底しています。お急ぎの方や時間がない方は、下記のお問合せフォームよりご連絡ください。メールを確認次第、速やかに担当者からお見積りと今後のスケジュールについて、ご案内させていただきます。
ご理解のほど、何卒、よろしくお願いいたします。
4.全省庁統一資格の取得方法がわからないという人へ

「手続きを自分でやろうか、それとも専門家に外注しようか?」
「手引きやマニュアルは、どこにあるのか?どこを探せばよいのか?」
と全省庁統一資格の取得方法で悩んでいるうちに、どんどん時間が過ぎてしまいます。「案件が目の前に迫っている」「期限がすぐ間近」という場合には、躊躇なく、専門家に外注し、スピード申請を依頼したほうがよさそうです。
たしかに、自分で手引きを見たり、マニュアルを確認したりしながら、全省庁統一資格を取得することはできなくはないかもしれません。しかし、そういった手続きに関する作業は、本当に皆さんが行うべき作業でしょうか?
- 代表取締役である社長は、会社の経営を
- 営業マンは、取引先への営業を
- 総務の人は、給料計算や社内管理を
- 現場作業員の方は、現場での安全な作業を
といったように、それぞれの大事な業務があるはずで、全省庁統一資格の取得手続きに時間を割く余裕はないのではないでしょうか?
みなさんの目的は、「全省庁統一資格を取得すること」でしょうか?それとも「全省庁統一資格を取得した後に、案件を落札すること」でしょうか?まさか「全省庁統一資格を取得することが最終目標だ!」という人はいないはずです。誰しもが、資格取得後の案件落札を目標にしているはずです。
そうであるならば、「全省庁統一資格の取得」は事前準備の段階で、スタート地点に立つ前の段階です。事前準備は、早く終わらせてスタート地点に早くたった方が有利なのは、言うまでもありません。
もう、お分かりですね。
- 手続きが苦手なのであれば、外注すれば良いのです。
- うまくできるか不安な人は、専門家にお任せすれば良いのです。
- 時間がないのであれば、プロに依頼するべきなのです。
全省庁統一資格は最大で3年間有効です。また、全ての省や庁の入札に参加できる規模の大きい資格でもあります。そんな資格を安心かつ安全に、しかも自分でやるより早く取得できるのであれば、専門家に外注しない手はありません。専門家に外注すると費用が掛かるという人もいるかもしれませんが、皆さんが案件を落札することができれば、専門家に外注した費用などは、すぐにペイできるはずです。
もう、迷っている場合ではありません。弊所は、複数の専門スタッフが在籍する法人です。御社からの依頼を受けた際には、チーム体制で業務を受任するため、タイムロスや時間の無駄なく、正確かつ迅速に申請手続きを遂行することができます。全省庁統一資格の取得でお困りの際は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドにご依頼ください。
みなさまに代わって、「納税証明書や登記後謄本の取得」「全省庁統一資格の申請」「結果通知書の受領」を責任をもって、代行させて頂きます。