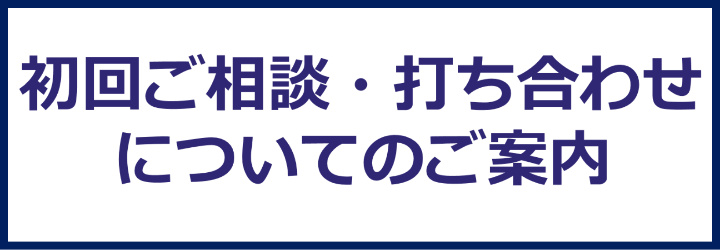私たちは「担当者個人の経験」ではなく、「法人組織としての体制」で申請を支援します。だからこそ、抜け漏れなく、安心して許可取得を進めていただけます。初めての方も、更新や追加の手続きをお考えの方も、ぜひスマートサイドにご相談ください。

- 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい!
- 産廃許可更新の期限が近づいているので、手続きを外注したい!
- 書類の収集・作成・提出など、産廃許可取得の一切を依頼したい!
- 東京都だけでなく、神奈川県や埼玉県や千葉県でも許可を取得したい!
上記のようなことでお困りの方はいらっしゃいませんか?
その他にも、「個人事業主でも産廃許可をとれるのかどうか?」「講習の受講はどうすればよいのか?」「積替え保管ありにするにはどうすればよいのか?」など行政書士法人スマートサイドには、産廃許可申請に関連するお問い合わせを頂いております。とくに、「東京都」を中心とした「埼玉県・千葉県・神奈川県」など、ご依頼が非常に多いです。
もちろん、その他の県での申請手続きを行っていないわけではありませんが、東京都内に事務所があるので、東京都の産廃許可申請に関するご依頼が多いのが事実です。そこで、このページでは、産廃許可申請に関する基本的なことを東京都の手引きに添って、分かりやすく解説して行きたいと思います。

東京都をはじめとした1都3県の産廃許可申請を得意とする。「登録車両20台以上」「1都6県への申請」など、規模の大きい会社の手続きも数多く受任。建設業許可や法人設立分野にも精通しているため、「会社経営に必要な許認可手続きを一括して依頼できる」と信頼が厚い。電子書籍「東京都の積替え保管ありの産廃許可取得の手順と注意点」を出版。インタビューは、こちら。
【1】産業廃棄物収集運搬業の許可とは(Q&A)
産業廃棄物収集運搬業の許可について、全く知識を持っていらっしゃらない方からの問い合わせも多々あります。どんなことでもそうですが、はじめは何もわからないのも無理はありませんね。ましてや、産廃収集運搬業の許可申請は、だれでも簡単にできるものではありません。
普段は目にしないような書類や、特殊なルールを理解していないと、なかなか許可取得にはたどり着けません。そこで、以下では、よくある相談を『「疑問」と「回答」』、『行政書士法人スマートサイドからのアドバイス』といった形で分かりやすくまとめてみました。
「疑問」と「回答」
疑問1:そもそ産業廃棄物収集運搬業の許可とは、何ですか?
(回答1)
まず、そもそも、産業廃棄物収集運搬業の許可とは「何?」なのでしょうか?産業廃棄物を収集し、運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。例えば、工事現場から出た「がれきや木材」、製紙工場から出た「紙くず」、食肉処理工場から出た「動植物性残渣」などを運ぶには、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
疑問2:どこで許可を取ればよいのですか?
(回答2)
東京都内にある会社だからといって、「東京都知事許可を取得すればよい」というわけではありません。
どこの許可を取得するかは、産業廃棄物の「収集元」と「運搬先」がどこかによります。例えば、「収集元」が東京都新宿区の工事現場で、「運搬先」が東京都国立市の処分場であれば、「収集元」も「運搬先」も、ともに東京都内なので、東京都知事許可を取得すればOKです。
一方で、「収集元」が東京都新宿区の工事現場で、「運搬先」が埼玉県の処理施設であった場合には、東京都知事許可と埼玉県知事許可の両方を取得しなければなりません。
このように産廃許可は「収集元」「運搬先」の両方の自治体で取得することが必要になります。
疑問3:個人事業主でも許可を取ることはできるのでしょうか?
(回答3)
もちろん個人事業主の方も、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することは可能です。むしろ、産業廃棄物を収集運搬する以上、個人事業主の方であったとしても、産廃許可を取得しなければなりません。個人事業主の方で「法人じゃないと許可を取得するのは難しいのでは?」という不安を抱えている方がいらっしゃいますが、法人だから取りやすい、個人だと取りにくいといったようなことはなく、産廃許可取得の難易度は、個人でも法人でも変わりません。
弊所のお客様の中には、従業員を雇わず1人で業務を行っている個人事業主であるにも関わらず、「東京都」「神奈川県」「千葉県」の1都2県の産廃許可を取得した方もいらっしゃるくらいです。
疑問4:許可を取るには、「講習の受講」が必要と言うのは本当ですか?
(回答4)
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、「日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講していることが必須です。講習会を受講し、効果測定に合格すると修了証が届きます。この修了証は、産廃許可申請の際に必要な書類です。講習会の修了証がなくても、産廃許可申請を行うことはできますが、講習会の修了証のコピーを提出してからでないと、許可が下りません。
疑問5:許可は永遠に有効なのですか?
(回答5)
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は5年です。5年以内に更新申請をしないと、産廃許可が失効してしまいます。有効期間は、許可証に記載されていますので、確認してみてください。
疑問6:許可を取るのに都庁や県庁に支払う手数料はいくらですか?
(回答6)
新規許可を申請する際に、法定手数料として81.000円を都庁や県庁に支払うことになります。申請先自治体1か所につき81.000円です。もし仮に、東京都、埼玉県、千葉県へ申請する場合には、それぞれに81.000円ずつ、合計で243.000円の申請手数料が必要になります。この申請手数料81.000円は、行政書士に依頼するか否かに関わらず、必ず都庁や県庁に支払わなければならない法定の手数料です。
疑問7:「積替え保管あり」って何ですか?
(回答7)
「産業廃棄物収集運搬業の許可」という場合、通常は「積替え保管なし」を言います。この「積替え保管なし」とは、「収集元」から「運搬先」までの間、自社施設に廃棄物を保管したり、自社施設で廃棄物を積み替えたりすることがない場合を言います。
一方で「収集元」から「運搬先」に廃棄物を運搬する間、自社施設に廃棄物を保管したり、自社施設で廃棄物を積み替えたりする場合には、「積替え保管あり」の許可が必要になります。
行政書士法人スマートサイドからのアドバイス!
上記の「疑問」と「回答」の中で特に注意が必要なのは、4番目の講習会の受講についてです。日本産業廃棄物処理振興センターの講習会は、いつでもどこでも開催しているわけではありません。お目当ての会場があったとしても満席であれば、他の日時・他の開催場所を探さなくてはなりません。
また、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページの、どの講習会に申し込みをすればよいのか?ネットで申し込みをするにはどうすればよいのか?など、初めての方は苦労すると思います。もし、産廃許可申請のみならず、講習会の受講についても一括して依頼したいという方がいれば、ぜひ行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。
【2】産業廃棄物とは
では、そもそも産業廃棄物とは、一体どういったものをいうのでしょうか?以下では、東京都環境局のホームページに掲載されいてる「産業廃棄物お種類」をわかりやすくまとめました。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物とは、以下の20種類を言います。
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.紙くず
8.木くず
9.繊維くず
10.動植物性残さ
11.動物系固形不要物
12.ゴムくず
13.金属くず
14.ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
15.鉱さい
16.がれき類
17.動物のふん尿
18.動物の死体
19.ばいじん
20.政令第13号廃棄物
より詳しく知りたい方はhttps://sanpai-web.jp/sanpai-shurui/を参考にしてみてください。行政書士法人スマートサイドの産廃許可専門サイトです。弊所にご依頼されるお客様の中で特に多いのは、「廃プラ」「紙くず」「木くず」「がれき類」など、建設現場から排出される廃棄物を取り扱う方が多いです。
一般廃棄物との違い
産業廃棄物と一般廃棄物との違いは、事業活動によって生じた廃棄物か否かによって区別されます。例えば、家庭から出るゴミは、事業活動によって生じた廃棄物ではないので、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物に該当します。よって、家庭ごみを収集するには、産業廃棄物収集運搬業の許可ではなく、一般廃棄物収集運搬業の許可を取得することが必要です。
【3】産廃収集運搬許可を取得するのに必要な書類
産業廃棄物収集運搬業の基本的知識を抑えることができたところで、実際に産廃許可を申請する際に、必要な書類について、東京都の手引きを参考にしながら確認していきましょう。
(参考:東京都公式「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出など」)
|
申請書類等 |
提出の要否 | |||
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 個人 | |||
| 【申請書類(様式)】 | ||||
| 1 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 変更事項確認書(変更許可申請書)※新規許可申請の場合は不要 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 事前計画書の概要 | 〇 | 〇 | |
| 4 | 運搬車両の写真 | 新規許可申請の場合:すべての車両 | 〇 | 〇 |
| 更新許可申請の場合:新規登録する車両のみ | 〇 | 〇 | ||
| 5 | 運搬容器等の写真 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 資産に関する調書(個人用) | ― | 〇 | |
| 8 | 誓約書 | 〇 | 〇 | |
| 【申請者に関する書類】 | ||||
| 9 | 定款の写し | 〇 | ― | |
| 10 |
法人の登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) |
申請者 | 〇 | ― |
| 5%以上の株主 | 〇 | ― | ||
| 11 |
住民票 ※本籍が記載されたもの ※マイナンバーが記載されていないもの |
申請者 | ― | 〇 |
| 役員等(監査役・相談役・顧問を含む) | 〇 | ― | ||
| 5%以上の株主 | 〇 | ― | ||
| 令第6条の10規定する使用人 | 〇 | 〇 | ||
| 12 | 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書 | 申請者 | ― | 〇 |
| 役員等(監査役・相談役・顧問を含む) | 〇 | ― | ||
| 5%以上の株主 | 〇 | ― | ||
| 令第6条の10規定する使用人 | 〇 | 〇 | ||
| 13 | 申請者の許可証の写し |
新規許可申請の場合: 他に産業廃棄物に関する許可を有する場合には、当該許可証 |
〇 | 〇 |
|
更新許可申請の場合: 更新する許可に係る東京都許可証 |
||||
| 八王子市の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可を有する場合:当該許可証 | 〇 | 〇 | ||
| 【財政能力に関する書類】 | ||||
| 14 | 貸借対照表(直近3年分) | 〇 | ― | |
| 15 | 損益計算書(直近3年分) | 〇 | ― | |
| 16 | 株主資本等変動計算書(直近3年分) | 〇 | ― | |
| 17 | 個別注記表(直近3年分) | 〇 | ― | |
| 18 | 法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分) | 〇 | ― | |
| 19 | 所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分) | ― | 〇 | |
| 20 |
・経理的基礎を有することの説明書および記載者の資格証明書 ・返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることがわかる書類 |
〇 | 〇 | |
| 【技術的能力に関する書類】 | ||||
| 21 | 講習会修了証の写し | 〇 | 〇 | |
| 【施設に関する書類】 | ||||
| 22 | 自動車検査証の写し(使用する全車両分) | 〇 | 〇 | |
行政書士法人スマートサイドからのアドバイス!
とくに注意が必要な書類は、【財政能力に関する書類】の中にある「貸借対照表」「損益計算書」です。「赤字だから許可が取れない」とか「業績が悪いのが理由で許可が下りない」といったことはありません。しかし、都や県が定める一定の基準を満たしていない場合には、財政能力を証明する書類を別途求められることになります。公認会計士や中小企業診断士が証明する書類の提出を求められたりすることがあるので、注意が必要です。
【4】産廃許可申請ご依頼の手続きの流れ
(1)メールフォームからのお問合せ
まずは、下記メールフォームからご連絡をください(電話でのご相談は、原則としてお断りしています)。面談や打ち合わせが必要な場合には、別途、日時を調整のうえ、こちらからメールさせていただきます。頂いたメールに「お見積り」「許可取得までのスケジュール」「注意点」などを記載のうえ、返信いたします。
お見積りを確認して頂き、了承が得られれば、正式に手続きを開始させていただきます。
![]()
(2)講習受講の申し込み→講習受講
産廃の講習を受講していない方は、先に「受講の予約」と「受講」を済ませてください。講習の予約は、日本産業廃棄物処理振興センターのホームぺージから行っていただくことになります。講習会を受講し、効果測定に合格すると「修了証」が届きます。産廃許可申請を弊所にご依頼してくださるお客様に会切り、講習会の受講の予約についても弊所で代行することが可能です。講習会の受講の申し込みについても、可能な限り弊所で対応させて頂きます。
![]()
(3)「正式なご依頼」と「費用のお振込み」
委任状をメールまたは、郵送いたします。委任状は必要事項を記載し、押印のうえ、弊所に送り返してください。弊所への委任状の到着をもって「正式なご依頼」とさせて頂きます。「正式なご依頼」ののち、請求書を発行いたします。請求書発行後、5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
![]()
(4)許可申請の予約
「正式なご依頼(委任状の到着)」の後、各自治体に申請の予約をさせて頂きます。産廃許可を申請するには、東京都庁や埼玉県庁への予約が必要です。予約に空きがないと、申請日時が1か月程度先になる可能性もあります。
![]()
(5)申請書類の収集・作成
頂いた委任状で住民票・納税証明書などの必要書類を代理取得いたします。また、申請書類の作成に必要な情報(廃棄物の種類や量、運搬先の情報など)をメールでヒアリングし、申請書類を作成します。
![]()
(6)申請書類提出
(4)で予約した日時に、申請手数料と申請書類を持って、都庁・県庁に申請に行きます。新規許可申請を郵送で受け付けている場合もありますので、郵送申請が可能な場合は、郵送申請を行うこともあります。不備や補正の連絡があれば、その都度対応いたします。。
![]()
(7)許可通知書の受領
申請に不備がなければ、3ケ月程度で御社に許可通知書が届きます。通常、標準処理期間は60日(土日祝日、年末年始を含まない)となっていますが、状況によっては、もう少し時間がかかる場合もあります。
![]()
(8)営業開始!!
許可通知書が届けば、晴れて営業を開始することができます。
【5】産廃許可申請を行政書士法人スマートサイドに依頼するメリット
メリット1:産廃許可申請に精通
このホームページの記載から、すでにお分かりいただけると思うのですが、行政書士法人スマートサイドは、「産廃許可申請」を得意とした行政書士事務所です。産廃許可申請は行政書士なら誰でもできる簡単な業務ではありません。
東京都と埼玉県では、申請のチェックポイントが異なります。必要書類の収集もすべて弊所で行います。行政書士法人スマートサイドは、さまざまな経験を通して、お客様に最も負担の少ない方法で、かつスピード申請を行うことができる、数少ない行政書士事務所です。
メリット2:1都3県の複数申請にも一括対応
お客様の中には、営業範囲を広げるために東京都内だけでなく、埼玉県・千葉県・神奈川県でも産廃許可が欲しいという方が非常に多くいらっしゃいます。そんな時こそ、行政書士法人スマートサイドの出番です。
複数申請は、申請先の件数に応じて、書類も2倍・3倍に増えていきます。また、実際に埼玉県庁や神奈川県庁に足を運ばなくてはなりません。不慣れな場合、かなり手こずってしまいます。行政書士法人スマートサイドは、1都3県の複数申請にも対応しております。
まとめてのご依頼は、喜んで対応させて頂きます。
メリット3:「積替え保管あり」の許可にも対応
行政書士事務所の中には、ホームページで産廃専門を表記しているのにも関わらず、「積替え保管あり」の申請には対応していない事務所もあります。「積替え保管あり」の申請は、難易度が高いため仕方ないかもしれませんが、それではお客さまからのご要望に応えられませんね。
行政書士法人スマートサイドは、東京都内の積替え保管ありの産廃許可申請にも対応可能です。23区内の住宅地にある積替え保管施設で、積替え保管ありの許可を取得した実績があります。
メリット4:スケジュール管理によるスピード申請
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには….「1.講習会の申し込み 2.講習会の受講 3.申請の予約 4.申請書類の収集・作成」など、やることが盛りだくさんです。しかもスケジュール管理をしないと講習会を受講し忘れたり、申請の予約日時に間に合わなかったりと、かえって時間を浪費してしまうことになりません。
行政書士法人スマートサイドは、初回面談~許可書の受領までの一連の流れを徹底的にスケジュール管理し、すこしでも早い許可取得を実現させています。
メリット5:個人事業主の方を徹底支援
「①個人事業主の方が産廃許可を取得する場合」と「②個人事業主が法人成りしてから産廃許可を取得する場合」とでは、手続きの流れが大きく異なります。どちらを選ぶのかは、個人事業主の方次第です。行政書士法人スマートサイドでは、①の場合でも②の場合でも、どちらでも対応することが可能です。
「個人のまま産廃許可を取得したい」「会社を設立してから産廃許可を取得したい」といったご本人の希望に沿う形で手続きを進めさせて頂きます。
【6】行政書士法人スマートサイドに依頼した場合の費用
料金一覧
| 申請先 |
行政書士報酬 (税込み) |
申請手数料 | 御社負担分 |
|---|---|---|---|
| 1か所あたり | 110.000円 | 81.000円 | 191.000円 |
複数自治体同時ご依頼は2件目以降50%OFF
複数の自治体に同時申請が必要な場合、2件目以降の行政書士報酬は50%OFFの税込み55,000円にて対応させて頂きます。
必要書類の取得手数料について
上記の費用以外に、住民票や納税証明書などの取得費用は、1通あたり2,200円をご請求させて頂きます。例えば、住民票1通2,200円、会社の登記簿謄本1通2,200円、登記されていないことの証明書1通2,200円などです。
費用のお支払い時期について
弊所では、正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
【7】産廃許可申請をご検討している方へ

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。産廃許可取得のイメージは湧いてきましたか?産廃許可申請は、必要書類を収集するのが大変であるのはもちろんのこと、実際に都庁や県庁まで申請に行くことが必要です。また、申請のためには、事前に予約を入れなければならないなど、手間がかかります。
さらに、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講していなければ、そもそも、産廃許可を取得できないなど、特殊なルールもあります。このように産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、時間も労力もかかります。
行政書士法人スマートサイドは、事業者の皆さんに代わって産廃許可申請の代行手続きを行うことを、とても得意とする事務所です。
産廃許可申請でお困りの方は、自分でやろうとせずに、外部の専門家に外注してみてはいかがでしょうか?本業に集中できますし、書類の書き方や集め方で頭を悩ませる必要もなくなります。このホームページをお読み頂き、ちょっとでも気になるようであれば、ぜひ行政書士法人スマートサイドにご連絡を下さい。
皆様の産廃許可取得に少しでも貢献できれば幸いです。