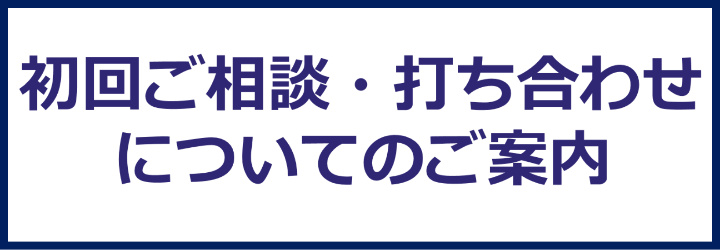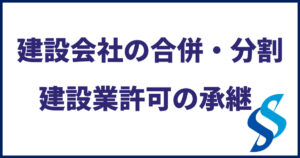
■ 建設業許可を別会社に譲渡したいと考えている
■ 会社を分割して建設業部門を別法人に独立させたい
■ 建設業許可会社との合併(M&A)するので許可を引き継ぎたい
という人はいらっしゃいませんでしょうか?
建設業許可が絡む「合併・分割・事業譲渡」において「建設業許可業者としての地位・建設業の許可番号・過去の実績」を引き継ぐことができるかどうかは、とても大きな問題です。
- 建設業許可の番号や許可業者としての地位が途切れてしまわないだろうか?
- 本当にこのまま、建設業を続けていけるのだろうか?
- 建設業許可の消滅や、取り直しにならないだろうか?
- 建設業許可業者としての地位を本当に引き継げるのだろうか?
- 500万円以上の工事を請負うことができなくならないだろうか?
といった点が、主に悩みの種かと思います。事業の承継、合併、分割といった会社の運命を左右する手続きと併せて、建設業許可の存亡がかかっているわけですから、皆さんが不安に思うのも無理はありません。そこで、このページでは、建設業許可の取得や維持の手続きの専門家である行政書士法人スマートサイドが、令和2年10月に改正された建設業法のうち「建設業許可の事業承継」=「認可申請の手続き」について、専門家の立場から、わかりやすく解説させて頂きます。

建設業許可の新規取得・維持の手続きの専門家。会社分割に伴う大臣許可の事業承継、親子会社の合併に伴う都知事許可の事業承継など、「許可の承継」「認可申請手続き」を多数経験。自身の経験や専門知識をフルに使って、建設会社に寄り添う姿勢が高く評価されている。「建設会社の社長が読む手続きの本(第2版)」を出版。「建設業許可を確実に取得する」ためのインタビューは、こちら。
(解説動画のご案内)
建設業許可の承継制度や認可申請についての解説動画をYouTubeにアップしました。「認可」「事業承継」について、簡単に理解したいという人は、こちらの動画を参考にしてみてください。
行政書士法人スマートサイドでは、会社分割や合併に伴う建設業許可の承継に関する相談、手続きの依頼を承っています。認可申請の書類の準備はもちろん、後日提出書類の提出、許可承継に関する具体的なアドバイスも可能です。建設業許可会社の分割・合併・事業承継に関するご相談は、ぜひ、こちらのページからメールにてご連絡ください。
令和2年10月の建設業法改正の概要
令和2年10月に建設業法は以下のように改正されています。第2章に「4節:承継」を新設し、17条の2では「譲渡・譲受け・合併・分割」について規定し、17条の3では「相続」について規定しています(参考:「e-GOV法令検索:建設業法」はこちら。)
(改正前)
改正前の建設業法では、建設業の事業譲渡や、建設会社の合併・分割があった際には、現在持っている建設業許可を取り下げて(廃業届を提出して)、再度、新たな建設業許可を取得しなおさなければなりませんでした。
しかしこれだと
- 建設業許可番号が変わってしまう
- 建設業許可業者としての地位を引き継ぐことができない
- 経営事項審査の結果を引き継ぐことができない
- 廃業してから新たに許可を取得するまでに500万円以上の工事を受注することができない
といった不都合が生じていました。せっかく、建設業の事業譲渡や、建設会社の合併・分割をして会社の再編を行おうとしているのに、「建設業許可業者の地位を引き継げない」「新たな許可を取得するまでは未許可業者になってしまう」というのでは、会社を再編するメリットが失われてしまいます。
(改正後)
そこで、上記の不都合を解消するべく、令和2年10月に、建設業法17条の2、17条の3を改正し、「第4節:承継」という条文を設けることによって、あらかじめ「事前の認可」を得ることによって、建設業許可業者としての地位を引き継ぐことができるようにしたわけです。この結果、建設業許可業者としての地位はもちろんのこと、建設業許可番号、経営事項審査の結果といった建設業許可に関する権利や義務のすべてを承継することができるようになりました。
当然のことながら、建設業許可を新たに取り直す必要も、事業承継(法人成り、事業譲渡、合併、分割)に伴って未許可の期間が発生するという不都合も、解消されたわけです。
建設業の承継とは?
建設業許可業者としての地位を承継(引き継ぐ・譲り渡す・譲り受ける)するために「認可制度」が、創設されたわけですが、「承継」とはどういったことを言うのでしょうか?
この点については、会社法の知識も必要になってくるかもしれませんが、細かい法律論は抜きにして、大まかにわかりやすく説明させて頂きます(なお、実際の建設業法においては第17条の3に相続の記載があります。しかし、個人事業主が死亡した場合の相続については、いわゆる「法人の事業承継」とは異なるため、このページでは説明を割愛させて頂きます。)
個人事業主の法人設立
建設業を営む個人事業主が新たに法人を設立する場合(法人成りする場合)、事前に認可申請を行い認可を受けることによって、個人事業主時代の建設業許可の地位を新たに設立した法人に引き継がせることができます。
このページの最初で説明した通り、建設業法の改正前は「現時点において建設業許可を持っている個人事業主が、法人を設立する場合」でも、建設業許可を引き継ぐことができず、個人事業主としての建設業許可を取り下げて(廃業届を提出し)、あらたに設立した新設法人で建設業許可を取得しなおさなければなりませんでした。許可番号も新たに付与されるため従前の許可番号を継続して使用し続けるということもできませんでした。
しかし、新たに創設された認可制度を利用することによって、現に建設業許可を持っている個人事業主が、法人を設立する場合には、現在保有している建設業許可(番号)を引き継ぐことができるようになりました。
法人同士の事業(建設業)の売却
建設業(会社の建設部門)を他の会社に売却するようなケースでも、認可制度を利用して、建設業許可を承継することができます。
たとえば、建設業と不動産業を行っているA社の場合。建設業許可を欲しがっているB社に建設業部門を売却し、自らは建設業から撤退する、もしくは、採算の取れる不動産業に専念するという例が、挙げられます。この場合も、B社は、あらたに自ら建設業許可を新規で取得するという方法を取らずに、事業の譲受(建設業部門の譲受)とともに、A社の建設業許可業者としての地位を承継することができることになります。
会社の合併
会社の合併には、複数の会社が合併して新たな会社を設立する新設合併と、一方の会社が他方の会社に吸収される形で合併する吸収合併の2つがあります。事業の譲渡(売却)の場合は、建設業部門を譲り渡した側の会社は、その後も消滅せずに、存続します。しかし、合併の場合、新設合併では既存の会社の法人格はすべて消滅、吸収合併では吸収される会社の法人格が消滅するといった点に、大きな違いがあります。この複数会社の合併の際にも、認可制度を利用すれば、承継先の会社が承継元の会社の建設業許可を引き継ぐことができます。
たとえば、「建設業許可を持っているC社」を「建設業許可を持っていないD社」が、吸収合併する場合。D社は、C社の建設業許可業者たる地位を吸収合併とともに引き継ぐことができます。資本力の大きいD社が、建設業界へ進出するにあたって、手っ取り早く建設業許可業者であるC社を買収し、建設業許可業者たる地位を手に入れるという例が、挙げられると思います。
また同じグループ会社の「E社(建設業許可業者)」と「F社(建設業未許可業者)」が合併し、グループ再編に伴い「新たなG社を設立する」ようなケースでは、E社の建設業許可を、新設会社であるG社が引き継ぐことができるようになります。
会社の分割
会社の分割には、1つの会社の分割後にあらたな会社が設立される新設分割と、分割した会社の一部を既存の会社に吸収させる吸収分割の2つがあります。事業の売却(事業譲渡)、合併と同じように、会社の分割の場合も、認可の手続きを経ることによって、建設業許可を承継させることが可能です。たとえば、「建設業許可を持っているH社」が、100%子会社(I社)を設立し、そのI社に建設業許可業者たる地位を承継させるという方法が、具体例として挙げられると思います。
認可を受けて事業承継させるための5つのルール
「個人事業主の法人成り」「法人同士の事業(建設業)の売却」「会社の合併」「会社の分割」の際に、建設業許可を承継できるとしても、まったくの無制限(フリーハンド)で認められるわけではありません。そこで、事前に理解しておいた方が良い5つのルールについて、解説させて頂きます。
認可の申請先
認可申請をする際の、申請先は、以下のように条件ごとに異なっています。
譲渡人が大臣許可の場合
譲受人の許可状況に関係なく、認可の申請先は、管轄の地方整備局になります。
| 【条件】 | 【申請先】 |
|---|---|
| 譲渡人が大臣許可の場合 | 管轄の地方整備局 |
譲渡人が都道府県知事許可の場合
原則として、該当する都道府県に申請することになります。但し、例外として、譲受人が大臣許可業者である場合、および譲受人が他の都道府県知事許可業者の場合、譲受人の管轄の地方整備局が、認可の申請先となります。
| 【条件】 | 【申請先】 |
|---|---|
| 譲渡人が都道府県知事許可の場合 | 該当する都道府県 |
| 譲渡人が都道府県知事許可で、譲受人が大臣許可の場合 | 管轄の地方整備局 |
| 譲渡人が都道府県知事許可で、譲受人が他の都道府県知事許可の場合 |
このように、認可申請をどこに行えばよいのか?については、細かく場合分けされているので、もしわからない場合は、都道府県もしくは各地方整備局に問い合わせをして確認するようにしてください。
認可申請の時期
事業譲渡・会社合併・会社分割といった事業承継の事実が発生するよりも前に、認可申請をして認可を得ていなければなりません。承継の事実が発生してから、承継日よりも前に、遡って認可することはできません。
認可申請の受付時期については、各自治体によってばらつきがあります。東京都の場合は「承継予定日の2か月前から25日前まで」、神奈川県の場合は「承継日の3か月以上前」といったように指定がありますので、その期間に認可申請を行えるように、事前にスケジュールを調整しておく必要があります。
承継の対象
承継先は、承継元の全部の建設業許可を承継する必要があります。一部の建設業許可のみを承継することはできません。もし仮に、承継元の有する許可業種のうち、承継しない業種がある場合には、認可申請の前までに承継元が廃業届を出して、建設業許可の一部廃業をしていなければなりません。
同一業種が承継対象の場合
1つの建設会社が、1つの業種について「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の両方を保有することができないため、承継によって同一業種の「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の両方を保有することになる場合には、不要な方を認可申請前に、廃業しておく必要があります。
営業所技術者について
営業所技術者は、承継以前の者が引き続き、常勤している必要があります。つまり、承継される許可業種の営業所技術者は、承継予定日以降も原則として、業種ごとに同一の営業所技術者が引き継がなければなりません。
もし、仮に承継予定日時点で、異なる者を営業所技術者とする場合、変更届の提出が必要になります。
認可を受けて事業承継させる際に必要な書類
ここまで「建設業法の改正→建設業の承継パターン→事業承継させるためのルール」といった流れで、建設業許可を承継する際の手続きについて、見てきました。以下では、建設業許可を引き継ぐ際に、実際に必要となる書類について「認可申請の際に必要になる書類」と「承継の事実が発生した後に必要になる後日提出書類」の2つに分けて、解説していきます(東京都の手引きを参考に承継先が建設業許可を持っているケースで必ず必要になる書類を一覧にしました)。
認可申請の際に必要な書類
(本冊)
| NO | 提出書類 |
|---|---|
| 1 | 譲渡/合併/分割認可申請書 |
| 2 | 役員等の一覧表 |
| 3 | 営業所一覧表 |
| 4 | 営業所技術者一覧表 |
| 5 | 使用人数 |
| 6 | 営業の沿革 |
(別とじ)
| NO | 提出書類 |
|---|---|
| 1 | 別とじ用表紙 |
| 2 | 営業所技術者証明書 |
| 3 | 技術者要件を証明する書類 |
| 4 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
(確認資料・添付資料)
| NO | 提出書類 |
|---|---|
| 事業譲渡 |
事業譲渡契約書の写し+株主総会議事録 |
| 合併 | 合併方法や条件の記載された書類+合併契約書の写し+合併比率説明書+株主総会議事録 |
| 分割 | 分割方法や条件の記載された書類+分割契約書の写し+分割比率説明書+株主総会議事録 |
承継先が承継元の建設業許可を引き継ぐには、事業承継の事実が発生する前に「認可申請をして認可を受けておくこと」が必要です。万が一、「認可申請」および「認可」の後に、建設業の譲渡・売却、会社の合併・分割が取りやめになった場合には、「認可」や「承継先への建設業許可」が取り消されることになります。このような事態を防ぐために、認可申請の時点で、「譲渡・分割・合併などの事業承継が適正な手続きで行われているか?」「意思決定が適正に行われているか?」を確認するための資料として、事業譲渡契約書、合併・分割契約書といった契約書類が必要になります。
承継の事実が発生した後に提出が必要な書類
(後日提出書類)
| NO | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 1 | 定款 |
30日以内 |
| 2 | 承継直後の時点における財務諸表 |
30日以内 |
| 3 | 営業の沿革 |
30日以内 |
| 4 | 所属建設業者団体 |
30日以内 |
| 5 | 登記事項証明書 |
30日以内 |
| 6 | 法人設立届または事業開始届 |
30日以内 |
| 7 | 法人番号を証明する書類 |
30日以内 |
| 8 | 承継日における経管および専技の常勤性資料(※) |
2週間以内 |
| 9 | 健康保険等の加入状況 |
2週間以内 |
| 10 | 社会保険の加入証明資料 |
2週間以内 |
| 11 | 営業所の確認資料 |
2週間以内 |
※経営業務管理責任者の常勤性の確認資料について
経営業務管理責任者(常勤役員等)が常勤していることは、建設業許可の要件です。そのため、承継元と承継先で経営業務管理責任者を変更する場合には、変更日の旧経管の常勤性の確認資料も必要になります。この点については、通常の経管変更手続きと同様です。
※営業所技術者の常勤性の確認資料について
営業所技術者については、原則として、承継以前の者が引き続き、常勤していなければなりません。そのため、変更が必要な場合には、おそくとも承継後2週間以内に変更届を提出する必要があります。
建設業許可の事業承継でお困りの方は、ぜひスマートサイドへ

さて、ここまでお読みいただいて如何でしたでしょうか?確かに法律が改正されたおかげで、建設業の売却、譲渡、分割、合併の際には、建設業許可を引き継げるようになりました。このおかげで、従前の許可番号を使い続けることができるようになりました。そういった意味では、「建設業許可の承継制度=認可の手続き」は、とても便利で使い勝手の良い制度ということができると思います。本文にも記載した通り、今までなら、いったん建設業許可を廃業し、新たに建設業許可を取得しなおさなければならなかったところ、認可申請を行うことによって、建設業許可を維持し続けることができるわけですから、企業再編やM&Aには、もってこいの制度です。
しかし、「手続きを行うためのルール」や「必要な書類」を見て頂ければわかる通り、認可申請のための手続きや必要書類の作成が簡単か?といえば、決してそうではありません。
たとえば、認可申請も認可も承継の事実が発生する前に、事前に済ませておかなければなりません。事前にスケジュールを組んで、「事業譲渡・合併・分割などの企業再編の予定」と「認可申請の時期」を調整する必要があります。合併や分割といった事業承継が行われてから、建設業許可を引き継がせる(維持する)ための認可申請を行っても遅いのです。また、認可の後に30日以内(もしくは2週間以内)に提出を求められる後日提出書類も重要です。万が一、経管や専技の常勤性を疑われるようであれば、認可も新しい許可も取り消されてしまう可能性があるわけです。
事業譲渡をはじめとした会社の再編自体は、弁護士や司法書士または税理士と相談することによって、手続きを進めていくことは可能かもしれませんが、こと建設業許可の手続きとなると、私たちのような建設業許可を専門に扱う行政書士の存在が必要不可欠です。東京都の手引きには「承継予定日については、可能であれば東京都と事前に協議して頂ければ幸いです」との記載があり、事前相談を求めています。
また、千葉県の手引きには「認可申請をする場合、事前に建設・不動産業課の窓口にご相談することをお勧めします。」神奈川県の手引きにも「事業承継の認可申請をされる場合は、あらかじめ建設業課へご相談ください。」埼玉県の手引きにも「承認申請を行うとするときは、事前に建設管理課建設業担当の窓口でご相談ください。」との記載があり、各行政庁への事前相談が必須です。
これは、決して大げさなことではなく
■ 認可の手続き自体が難しいこと
■ 必要となる書類が通常の新規申請よりも多いこと
■ 建設業許可の承継がうまく行かなければ、合併や分割といった企業再編そのものに大きな影響を及ぼすこと
■ 事前相談や事前協議を経て、認可をすることによって、行政としてもスムーズな承継を目指していること
のあらわれです。
行政書士法人スマートサイドは、創業以来、建設業許可の申請を専門に行う事務所として、いくつもの建設業許可取得の実績や経験があります。御社の事業承継の手続きについても、きっとお役に立てるものと確信しています。
建設業の売却・譲渡、建設会社の合併・分割をお考えの方は、ぜひ、こちらのページから行政書士法人スマートサイドにご相談下さい。みなさまからのご相談を心よりお待ちしております。