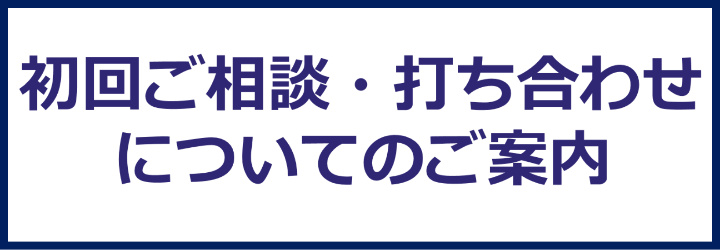みなさんの中には
- 第2種電気工事士の資格では建設業許可を取ることができない
- 第2種電気工事士は、建設業許可に必要な専任技術者になることができない
といったことを聞いたこと、見たことがある人はいませんか?
私のお客様の中にも、上記のようなお困りごとで、相談に来る方はいらっしゃいます。しかし、「第2種電気工事士の資格では建設業許可を取得することができない」ということも、「第2種電気工事士は、建設業許可に必要な専任技術者になることができない」ということもありません。
このページは、そんな誤解を解くために
という方のために記載しました。建設業者の中にも、行政書士の中にも、第2種電気工事士の資格では、建設業許可の専任技術者になることができないと思っている方が多いようです。しかし、このページを読んでいただければ、それは「だだの思い込み」であることがお分かりいただけると思います。
以下の説明を、皆さんが電気工事の建設業許可を取得する際の参考にしていただければ幸いです。
専任技術者になるためには?
まず、前提として、建設業許可を取得するためには、専任技術者(以下「専技」と省略する)が会社に常勤していなければなりません。そして、専任技術者の要件を満たすには、以下の3点のいずれかに該当しなければならないのが一般的です。
1.10年の実務経験があること
「内装工事の建設業許可を取得したいのであれば10年の内装工事の実務経験があること」「防水工事の建設業許可を取得したいのであれば10年の防水工事の実務経験があること」といったように、10年の実務経験を証明することによって、専任技術者の要件を満たすことが、可能です。
2.特殊な学科を卒業していること
仮に、10年の実務経験を証明することができなかったとしても、「特殊な学科(建築科・土木科・機械科など)」を卒業していれば10年の実務経験を3~5年に短縮できます。そのため、10年の実務経験を証明することができない人にとっては、特殊な学科の卒業経歴を使て、3~5年の実務経験を証明することが必要になります。
逆にいうと、「特殊な学科の卒業経歴がないのであれば、原則通り10年の実務経験の証明をしなければ専任技術者になることができない」ということが言えます。
3.国家資格を保有していること
「建築士」や「施工管理技士」といった国家資格を保有していれば、上記1.2の実務経験の証明は、原則として不要になります。実務経験を証明しなくても、特殊な学科の卒業経歴がなくても、国家資格を保有していることによって、建設業許可に必要な専任技術者になることができます。
電気工事業の専任技術者になるためには?
以上のように、一般的には上記の3点が建設業許可を取得する際の、専任技術者になるための要件になります。一方で、電気工事業の建設業許可を取得する場合、上記の一般論が当てはまらないケースがあります。
1.電気工事業の特殊性その1
まず、電気工事業の建設業許可を取得する場合の特殊性として、「10年の実務経験を証明しても専任技術者になることができない」といった点があります。


「10年の実務経験を証明すれば、専任技術者の要件を満たすのでは?」と思ったひとも多いかもしれません。しかし、この点が電気工事業の建設業許可を取得する際の特殊性なのですが、電気工事業の場合、無資格者が実務経験を10年積んでも、20年積んでも、専任技術者になることができません。
たとえば、内装工事の建設業許可を取得する場合には、内装工事の10年の実務経験を証明すれば専任技術者になることができます。とび・土工・コンクリート工事の建設業許可を取得する場合には、とび・土工・コンクリート工事の10年の実務経験を証明すれば専任技術者になることができます。
しかし、電気工事の建設業許可を取得する場合には、無資格者の実務経験は認められていないため、実務経験が10年あっても20年あっても、専任技術者になることができません。
2.電気工事業の特殊性その2
続いて、「第1種電気工事士/電気工事施工管理技士」の場合は、実務経験の証明なくして建設業許可を取得する際の専任技術者になることができますが、「第2種電気工事士」の場合、資格を持っているだけではダメで、免許交付後3年以上の実務経験を証明する必要があります。


「資格を持っている場合には、実務経験の証明は必要ないのでは?」と思った方もいらっしゃるかもしれませんね。たしかに、通常は、資格や免許を持っていると実務経験の証明は免除されます。しかし、電気工事業の特殊性その2として、「第2種電気工事士」の資格の場合には、免許交付後3年以上の実務経験を証明しなければ、建設業許可を取得する際の専任技術者になることができません。
第2種電気工事士の資格を持っている人は、第1種電気工事士や電気施工管理技士の資格を持っている人に比べて、多いと思いますが、第2種電気工事士の場合、電気工事士の資格を持っているにも関わらず、電気工事士の免許交付後3年以上の実務経験の証明が必要という点に注意をしなければなりません。
よくあるのが、「うちの会社には、1年前に第2種電気工事の資格を取得した社員がいるのたけど…」といったお問合せです。この場合、第2種電気工事の資格を取得したのが1年前である以上、「免許交付後3年」といった要件を満たすことができません。そのため、いくら「第2種電気工事の資格を持っている社員がいる」としても、その社員を専任技術者にして電気工事業の建設業許可を取得することはできないのです。
3.電気工事業の特殊性その3
最後に、電気工事の実務経験を証明するには、電気工事業の登録をしている会社もしくは電気工事業の登録をしている個人事業主の元での勤務経験であることが必要です。


電気工事業は登録制となっており、電気工事業を営むには「経済産業大臣」もしくは「都道府県知事」の登録を受けなければなりません(電気工事業の業務の適正化に関する法律:第3条1項)。もし仮に、登録をせずに電気工事業を営んだ場合は、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金(同法:36条1号)になってしまいます。
つまり、登録を受けずに電気工事業を営むことは違法です。この違法営業中の実務経験を建設業許可を取得する際の実務経験として利用できるとなってしまうと、建設業許可を取得するために「登録を受けずに電気工事業をしてしまおう」という違法行為の助長にもつながりません。
そのため第2種電気工事士が専任技術者になるために必要な免許交付後3年の実務経験は、「電気工事業の登録を受けている法人または個人の元での実務経験」というような限定的な解釈がなされるのです。
もっとも、一部の自治体では上記の法律に抵触しない電気工事であった場合など、特別な事情がある場合には、その旨の申立書を添付するなどして、実務経験の証明が認められるケースもあるようです。
- 10年の実務経験を証明しても専任技術者になることができない
- 免許交付後3年以上の実務経験を証明する必要がある
- 電気工事業の登録をしている会社(個人)の元での実務経験であることが必要
第2種電気工事士の資格で建設業許可を取得した申請実績
以下では、実際に行政書士法人スマートサイドが、第2種電気工事士の資格を使って、東京都の建設業許可(電気工事業)を取得した実績について、解説させて頂きます。皆さんの会社にも当てはまるようなケースがあると思いますので、ぜひ、参考にしてください!
| 実績NO | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 実績1 |
LED間接照明や電子機器の設計・製造をメインで行っている足立区のお客様からのご依頼です。第2種電気工事士の資格を使って、東京都建設業許可(電気工事業)を取得しました。 工事費自体は、500万円を超えることはないものの、電子機器などの部品代も含めると全体として設置工事費用が500万円を超えてしまうため、建設業許可を取得しなければなりませんでした。 |
|
| 実績2 |
電気通信工事と電気工事の2業種を同時に新規で取得した実績です。電気と電気通信のどちらか一方だと不便なので、まとめて一気に取得したいということでした。 電気工事と電気通信工事のどちらも、社長が専任技術者になりました。【電気通信工事については指定学科+5年の実務経験の証明、電気工事については第2種電気工事士の資格+3年の実務経験の証明】という組み合わせで、建設業許可を取得することに成功しました。 |
|
| 実績3 |
消防設備の設置や点検をメインに行っている会社が、すでに持っている消防工事業に電気工事業を追加した実績です。 消防設備の設置には電気工事も絡んでくるため、長年、電気工事の建設業許可も取得したいと思っていたらしいのですが、第2種電気工事士の取得+免許交付後3年の実務経験を証明することによって、念願だった電気工事業の建設業許可を取得することができました。 |
|
| 実績4 |
電気工事業の専任技術者を第1種電気工事士から、第2種電気工事士に変更したという珍しい実績です。 第1種電気工事士の資格者が会社を退職するにあたって、もし仮に、第2種電気工事士の資格を持っている社員に専任技術者を変更できなかった場合、電気工事業の許可を取り下げしなければ(廃業届を提出しなければ)ならないという、大変難しい案件でした。 |

まとめ
以上、まとめると、第2種電気工事士の資格を使って専任技術者になり、電気工事業の建設業許可を取得することは可能です。
しかし、免許交付後3年以上の実務経験の証明が必要なため、免許交付を受けてから3年以上たっている必要があります。また、その3年間の実務経験は、電気工事業の登録をしている会社もしくは電気工事業の登録をしている個人の元での経験である必要があります。
そして、東京都知事許可の建設業許可(電気工事業)を取得する場合、3年間の実務経験を積んだ会社での常勤性を証明するため、
- 健康保険証のコピー
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
- 法人用確定申告書(役員報酬明細)
などを準備しなければなりません。


如何でしたでしょうか?電気工事業の建設業許可は、簡単に取れそうですか?それとも、難しそうですか?
一般的に建設業許可を取得する手続きは、難しい部類の申請にあたります。書類が多いうえに、申請する自治体によってルールが異なるので、なかなかうまく行かず「許可を取得できなかった」「許可は取得できたけど、とても時間がかかった」という話は、よく聞く話です。加えて、電気工事業の許可は、他の種類の許可(内装工事や塗装工事など)に比べて、このページで記載した特殊性があるため、より難しく感じるかもしれません。
行政書士法人スマートサイドでは、このページに記載した実績以外にも、さまざまな経験・知識・実績がありますので、電気工事業の許可を取得したいと思っているみなさんのお役に立てること、間違いありません。
第2種電気工事士の資格を持っている、第2種電気工事士の資格を使って東京都の建設業許可を取得したいという方がいれば、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡を下さい。